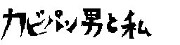HOME > 語学 > 日本語 > 草書の骨格 > 三十二日目
三十二日目
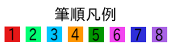
究、急、級、宮、求、球、去、橋、並、業
究

孫過庭を参考にした。
急

草書韻會を参考にした。
「心」の部分が三つの部品から成り立っていることについては、「心」参照。
級

草書韻會を参考にした。
糸へんについては、「糸」参照。
宮

上図は、書道字典に唐の張旭の字として載っていた形だが、宮の草書としてはこの形が一般的になっているようである。
上の口が「マ」下の口が「ム」になった形であろう。
懐素は「うかんむり」の点を異なる筆順で書いている。

ところで、宮の楷書は、唐の時代には

のようであり、上下二つ並んだ口を連絡する画はない。
求
「球」を学ぶために、まず「求」を学ぶ。

上図は王羲之を参考にした。
球

去

上は王羲之の字にもとづく。問題は、最後に書く、深緑に塗った画である。これが、つい書いてしまったオマケなのか、字体の欠くべからざる部分なのか。次に、王羲之の別の字を見てみる。

緑の画と、オレンジの画が離して書かれている。ここから考えると、オレンジの画はオマケではなくて、字体を構成する重要な部分だと判断できる。
橋

上図は、王献之を参考にした。
上図の草書では、「橋」のツクリ部分の上半分にある「大」の形で、右払いを欠いている。これは、下(欧陽詢を参考にした)のような唐の楷書と整合する(この場合、口の形はハシゴ型と同等)

ただし、上図の楷書の形は、「大」の上についている「ノ」を欠いていることに気づく。一方、最初に挙げた草書では、「ノ」が存在する。
漢の時代の字でこの部分に当たるところ(下図矢印)を見ると、楷書でこの部分を省略した字があるのもうなずける。

並
三年生の漢字「業」を学ぶために、「並」を見る。次図は王羲之を参考にしたもの。

問題になるのは、中段の \||/ の形である。草書では、この部分が三つのパーツから成り立っている。
下図で王羲之の別の字を見る。スポットライトを当てた部分は、二つのパーツに見え、問題の箇所は現代の活字と同じに四つのパーツからできていることになる。ここから、最初に挙げた型で、どの画が省略されているかを推測した。

業

上図は孫過庭を参考に書いたもの。一番上の \||/ 部分について、右から二番目の縦画が省略されたという推測については、「並」と同じセンスだと考えて、活字の画との対照を考えた。
(したがって、赤部分と緑部分の間隔より、緑部分と水色部分の間隔を広くとるのは、美的な要請である以前に、字体の要請するところであると言うことができる)
また、「羊」部分のふたつのツノが草書にないことについては、王献之の

のような形を見ると理解できる。
次に、ちょっとだけ \||/ 部分の筆順について考える。
唐の時代の楷書は、

のようであり(ちょ遂良を参考にした)、この形で \||/ 部分の筆順は現在学校で習うように、||\ / という順番になる。ところが、

のような形(欧陽通を参考にした)も書かれており、これは左から順番に|||/ と書くのが自然である。
もう少し古い時代ではどうか。[3]には、木簡にあった字として、

のようなものが載っていたが、これは完全に左から順に書いている。
次は王羲之の字を参考にした形。

実際に書いてみるとわかるが、左から順番に書くほうが自然である。
このように見ていくと、\||/ 部分を左から順に書くというのは、必ずしも草書特有の表現ではないと言っても差し支えなさそうだ。